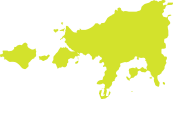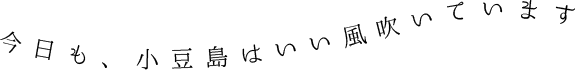歴史・文化
安田おどり

安田おどり
安田地区の伝承によれば、延宝年間(1673〜81)に、当時京都で名のあった安田出身の歌舞伎役者が郷土へのおくりものとして作ったと伝えられています。
その後、大坂から安田に移住した上方歌舞伎役者、初代嵐璃当(天保年間〜明治初年)によりさらなる試練工夫がなされ、今日の入庭(いりは)、手踊り、中歌、扇の手、出庭(では)の形式に完成されました。
現行の踊りは、手踊りと扇踊りの2種類。
手踊りの方の唄には『星ヶ城哀話』が唄いこまれ、『安田星ヶ城夜風のままにお妻悲しの恋物語』、『星ヶ城こそこの世の浄土波に任せた恋路の果ては』、『秋の風吹くお局塚に末の世までも哀れをとどむ』などと、7・7・7・7形の口説形式からなり、扇踊りの唄には『寒霞渓、内海の人情』などが唄い込まれ、7・7・7・5形となり、各節が独立した歌詞となっています。
扇の踊りの唄の章句の中には、江戸中期の小唄に近いものがあることも珍しい。
踊りは輪踊りの形式で、男はハッピ、黒い帯、鉢巻で団扇を持ち、女はユカタ、市松模様の文庫帯で扇を持って踊ります。
昔は旧盆の8月13・14・15日に踊っていましたが、今では8月14日に戦死者の追善、新仏の供養の目的で踊っています。



INFORMATIONご案内
| 日程 | 8月14日 ※毎年同日 |
|---|---|
| アクセス | 香川県小豆郡小豆島町安田 安田小学校グランド 安田公民館 |